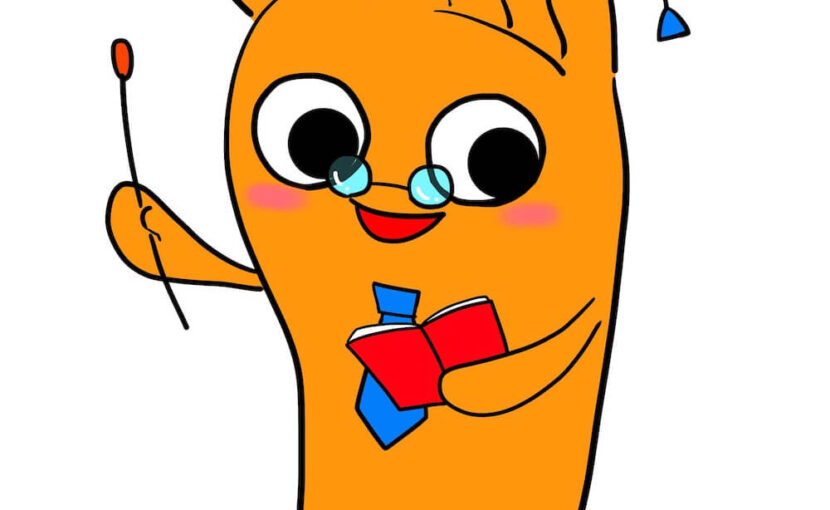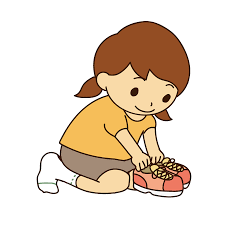巻き爪は、足に合わないサイズの靴を履いたり、悪い爪の切り方によって起こります。また加齢による運動不足も、巻き爪の原因となります。
巻き爪は、靴の履き方や歩き方、爪を正しく手入れすることで予防することができます。今回は、巻き爪にならないための方法についてお話しします。
足の生活習慣を見直して巻き爪を予防しよう
巻き爪は、靴のサイズやデザインが足の形に合っていないか、靴が正しく履けておらず、歩き方が悪くなることが原因で起こることが多いといわれています。
これらの理由以外にも、体質や遺伝的要因、加齢による運動不足で爪が変形してしまったり、伸びた爪の切り方が悪くて巻き爪になったりすることもあります。
巻き爪は、個人の生活習慣が原因となっていることが多いので、生活習慣などについて、専門家からアドバイスを受けて対処することで、ある程度は予防できるとも言えます。
巻き爪は、特に加齢による運動不足から、足の指の爪が皮膚を包むように曲がることでも起こりやすいといわれています。
しかしそれは原因のうちの一つにしかすぎません。
「足の指先のトラブルだから、放っておいても治る」と思って放置していると、傷口が化膿することもあるため、日ごろから爪や皮膚が痛まないよう、注意しなければなりません。
また痛みは、やがてそれらをかばうために、ひざや腰へ負担をかけ、それらを痛めることにもつながります。高齢者の場合は、転倒を避けるためにも早めに対策をとるようにしてください。
まずは靴の大きさや形、履き方をチェック]
巻き爪は、足の指に過剰に力がかかって、親指の爪がまっすぐに伸びることができないために起こると考えられています。
外反母趾がある人や足の形に合わない靴を履いていると、歩行中、足の指に過剰な力がかかりやすくなります。
靴を選ぶとき、その大きさは、足の指が少し広げられるゆとりがあるものにします。つま先は、5~10㎜の余裕があるのが理想とされています。
ヒールが3㎝以上の高さがある場合は、履く時間を限定するなど工夫して、できるだけ足に負担をかけないようにしてください。
ひも靴を履く時は、履くたびにかかとを合わせて、靴ひもをしっかりと結び、足の甲で固定するようにしましょう。靴ひもをゆるめに結んだまま、ほどかずに着脱をすることのないようにしてください。
歩いている時は、地面からの衝撃によって足腰や膝、股関節に負担がかかりやすくなります。かかと部分がしっかりとした靴を選ぶように心がけましょう。
足の爪は正しく歩くことで平らに伸びる
巻き爪の予防には、正しい靴を選ぶだけでなく、歩き方にも注意が必要です。
足の爪は歩く時に地面を踏むことで、足の指が下から力を受けて形が平らになります。日頃から、足の指でしっかりと地面を踏むように歩くよう心がけるのがよいですが、つま先が内側や外側を向くと、爪へ力が伝わりにくくなり、爪がゆがんで伸びて、巻き爪が起こりやすくなります。
【正しい歩き方】
歩く時は、頭のてっぺんが糸でひっぱりあげられているイメージを持ち、腕を後ろに振るようにします。
(1)つま先を正面に向けてまっすぐ足を出すようにします。
(2)着地はかかとから、重心は足裏全体にかかるようにします。
(3)上半身が前方に移動したら、小指側に重心を乗せるようにします。
(4)反対側の足が前に着地する時は、後ろの足の重心は親指へ移動し、親指を押すようにして地面を押して、足を持ち上げて前方へ移動します。
高齢者は運動不足になりがちで、歩くことも少ないので、巻き爪の発症リスクが高くなります。
この他にも、急に体重が増えると足への力のかかり方がアンバランスになり、巻き爪の原因となることがあります。
原因の中でも実はとりわけ目立つのが、足の指が立っている時に接地していない「浮き指」や外反母趾といった足のアライメント異常(足の形のトラブル)です。もちろん、体質、そして遺伝的要因も巻き爪の原因になりますが先天的なことが原因というよりも、足靴の環境、歩行習慣など含めた習慣的なものの方が大きく作用し、また大部分の方がこちらの原因だと推測されるケースが多いです。これらの症状は、サポーターやテーピングを使いながら、足の形を正常に戻し(機能的な状態を維持)、足指の使い方をリハビリすることで改善を目指していきます。

爪の切りすぎはNG
巻き爪は正しい爪の切り方で、日頃から予防しましょう。
爪切りは3~4週間に1度の頻度で行います。
深爪をすることのないよう、爪の長さを指の先端に合わせるか、それよりも1㎜程度長く切るようにします。角を少しだけ整える程度に切って爪の形を平らでまっすぐになるようにします(「スクエアカット」と言います)。
巻き爪防止効果が高い爪切りを使えば、手入れが簡単です。
テーピングを使って巻き爪防止効果を高める
靴や歩き方、爪のケアと同じように、巻き爪の予防に効果的な方法がテーピングです。少し痛みが出てきた時にテーピングをすることで、症状が和らぐこともあります。
自分でもできるテーピングの手順を2つ紹介します。
【1:痛む爪と皮膚の間を広げる】
テープの端を、痛む爪の横にテープが垂直になるよう、ギリギリのところに張って、強く引っ張りながら指の下をくぐらせて、爪の反対側へテープを出します。
指の下からくぐらせたテープは、指の斜め上側(足の甲側)にくるように引っぱり上げて張ります。次に、最初と反対側の爪の端からもテープを同じ要領で張ります。
【2:痛む爪と皮膚の間にテープを挟む】
痛む爪の両端と先端部分をテープで囲むように張る方法です。テープの端3㎜ぐらいが、爪にかかるように貼ります。
この時、引っぱりながら張る必要はありません。テープが張れたら、爪にかかった部分を、ピンセットを使って爪の下部分へ挟み込むように食い込ませていきます。
上記にご紹介したのは、あくまでも応急処置です。きちんと改善してくためには、専門家のもとでケアを受けることが大切です。
自分の巻き爪の原因が知りたいなら
たくさんある巻き爪や陥入爪、爪甲鉤彎症といった爪のトラブルの原因を自分で把握するのは難しいことです。巻き爪矯正院グループでは、巻き爪の原因を知ってもらうためのカウンセリングを大切にしております。それにより、巻き爪が再発が少しでも予防できるように協力させていただいております。
自分の巻き爪の原因を知ることでしっかりと巻き爪ケアをすることが健やかな足環境を保つための近道です。
巻き爪で悩んだら「切らない!痛くない!巻き爪専門院グループ」へお任せください
東京都内エリアなら
埼玉エリアなら
東北エリアなら
神奈川エリアなら